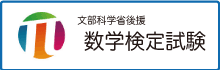月別アーカイブ: 2016年5月
地方で偏差値格差が生まれる理由
2016年5月31日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** 地方で偏差値格差が生まれ …
年をとっても勉強が必要
2016年5月30日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** 年をとっても勉強が必要 …
日本を救うイノベーター志向
2016年5月26日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** 日本を救うイノベーター志 …
ツケは自分に返ってくる
2016年5月24日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** ツケは自分に返ってくる …
SNS疲れしていませんか?
2016年5月20日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** SNS疲れしていませんか …
真珠湾と広島の違いをどう教えるか
2016年5月18日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** 真珠湾と広島の違いをどう …
当塾が高校生を見るわけ
2016年5月17日 ブログ
皆さんこんにちわ。 富山市山室の学習塾「茗溪進学会」塾長の澤木です。 読んでためになり、子供たちが幸せになるヒント情報を発信します。 どうかお付き合いください。 **************** 当塾が高校生を見るわけ …
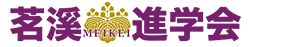
 お問い合わせ
お問い合わせ